「面白いから読む」では、受験には通用しない。高校入試の国語は、読解力・語彙力・思考力の総合勝負。中学生のうちに“読む筋力”をつけておくことが、合格への土台になる。今回は、たとえ退屈でも読む価値のある小説20冊を厳選。読んだ者だけが、差をつけられる。
高校受験生が小説を紙媒体で読むことには多くの利点があります。
まず、紙の本は視覚的・触覚的な刺激を提供し、集中力を高める効果があります。ページをめくる動作や紙の質感は、電子書籍にはない没入感を生み出します。また、紙媒体は目に優しく、長時間の読書でも疲れにくいというメリットがあります。
さらに、紙の本は書き込みやメモを取りやすく、重要な部分をすぐに見返すことができます。これにより、内容の理解が深まり、記憶に定着しやすくなります。受験勉強においては、長文読解力や語彙力の向上が求められるため、小説を読むことは非常に有益です。
最後に、紙の本を読む習慣は、試験本番での紙媒体の問題に対する適応力を高めることにもつながります。これらの理由から、高校受験生が小説を紙媒体で読むことは非常に重要です。
1.『かがみの孤城』 – 辻村深月
『かがみの孤城』は、中学1年生のこころが主人公の物語です。こころは学校でいじめに遭い、不登校になってしまいます。ある日、彼女の部屋の鏡が突然光り出し、こころはその鏡を通じて不思議な城に引き込まれます。
その城には、こころと同じように学校に行けなくなった6人の中学生が集まっていました。彼らは「オオカミさま」と呼ばれる狼の仮面をかぶった少女から、城の奥にある「願いの部屋」の鍵を見つけた者だけが願いを叶えられると告げられます。しかし、城にいられるのは日本時間の午前9時から午後5時までで、それ以降も残っていると狼に食べられてしまうというルールがありました。
こころたちは、最初はお互いに心を開けずにいましたが、次第に友情を深めていきます。彼らはそれぞれが抱える悩みや問題を共有し、支え合うことで少しずつ前向きになっていきます。特に、こころは自分の不登校の理由を話すことで心が軽くなり、他の子どもたちとも打ち解けていきます。
物語が進むにつれて、こころたちは「願いの部屋」の鍵を探し続けますが、なかなか見つかりません。そんな中、彼らは現実世界でも少しずつ変わり始めます。こころは母親や先生と話し合い、学校に戻る勇気を持つようになります。
最終的に、こころたちは「願いの部屋」の鍵を見つけることができませんでしたが、彼らの心には大きな変化が生まれました。友情や自己発見を通じて、彼らは自分たちの未来に希望を持つことができるようになったのです。
『かがみの孤城』は、いじめや不登校といった現実の問題を扱いながらも、ファンタジーの要素を取り入れた感動的な物語です。こころたちの成長と友情の物語は、読者に勇気と希望を与えてくれます。
2.『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』 – ブレイディみかこ
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、イギリスに住む日本人の母とアイルランド人の父を持つ「ぼく」の中学校生活を描いたノンフィクションです。主人公の「ぼく」は、カトリックの小学校から「元底辺中学校」と呼ばれる公立中学校に進学します。そこでは、さまざまな人種や背景を持つ生徒たちと出会い、日々の生活を通じて多くのことを学びます。
「ぼく」は、これまでの生活とは全く異なる環境に戸惑いながらも、新しい友達と出会い、彼らと一緒に成長していきます。例えば、移民の子どもたちや貧困層の子どもたちと接することで、差別や偏見について考えるようになります。また、ジェンダーの問題や文化の違いについても学び、自分の考えを深めていきます。
母親であるブレイディみかこさんは、「ぼく」の成長を見守りながら、彼が直面する問題に対して一緒に考え、サポートします。彼女は「ぼく」を一人の独立した人間として尊重し、彼の意見や感情を大切にします。この親子の関係は、読者にとっても共感できる部分が多いでしょう。
物語の中で、「ぼく」はさまざまな経験を通じてエンパシー(共感)を学びます。例えば、友達が差別的な発言を受けたとき、「ぼく」はその友達の立場に立って考えることの大切さを知ります。また、友達が困っているときに手を差し伸べることで、友情の大切さを実感します。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、現代社会の多様性や共生の重要性を教えてくれる一冊です。中学生にとっても、身近な問題を考えるきっかけとなるでしょう。この本を通じて、読者は自分自身や他人について深く考えることができるでしょう。
3.『エイジ』 – 重松清
『エイジ』は、中学2年生の高橋エイジが主人公の物語です。エイジは東京郊外の桜ヶ丘ニュータウンに住んでいて、ある夏、彼の町で連続通り魔事件が発生します。犯行は次第にエスカレートし、ついに犯人が捕まりますが、その犯人はエイジの同級生、タカやんでした。
エイジはこの事件をきっかけに、自分自身や周囲の人々について深く考えるようになります。彼は膝のけがでバスケットボール部を休部しており、部活を辞めるかどうか悩んでいました。そんな中、エイジは友達や家族、先生たちとの関係を見つめ直し、自分の気持ちや行動について考えます。
エイジのクラスメイトには、クールでプライドの高い藤田タモツや、お調子者のツカちゃん、エイジが片思いしている相沢志穂など、個性豊かなキャラクターが登場します。彼らとの日常のやり取りや、通り魔事件を通じてエイジは成長していきます。
特に、エイジがタカやんの犯行について考えるシーンは印象的です。エイジは「自分も同じような状況に置かれたら、同じことをしてしまったのではないか」と悩みます。しかし、家族や友達との関わりを通じて、エイジは自分とタカやんの違いを見つけ出し、少しずつ前向きになっていきます。
物語の中で、エイジは自分の膝のけがや部活の問題、友達との関係など、さまざまな困難に直面しますが、それらを乗り越えることで成長していきます。最終的に、エイジは自分自身を見つめ直し、未来に向かって一歩踏み出す勇気を持つようになります。
『エイジ』は、思春期の中学生が抱える悩みや葛藤をリアルに描いた作品で、読者にとっても共感できる部分が多いでしょう。エイジの成長とともに、読者も自分自身について考えるきっかけを得られるはずです。
4.『君たちはどう生きるか』 – 吉野源三郎
『君たちはどう生きるか』は、コペル君という中学生の男の子が主人公の物語です。コペル君は、学校や家庭でさまざまな出来事を経験しながら、自分の生き方について考えていきます。
物語は、コペル君が友達との関係や学校での出来事を通じて成長していく姿を描いています。ある日、コペル君は友達の浦川君がいじめられているのを見て、勇気を出して助けようとします。この出来事をきっかけに、コペル君は「正しいことをする勇気」の大切さを学びます。
また、コペル君にはとても尊敬している叔父さんがいます。叔父さんは、コペル君にさまざまな教えを与えてくれます。例えば、「人間はみんなつながっていて、お互いに助け合うことが大切だ」ということや、「自分の経験から学び、成長することが大事だ」ということを教えてくれます。
物語の中で、コペル君は自分の行動や考え方について深く考えるようになります。例えば、友達を裏切ってしまったときには、そのことを反省し、どうすればもっと良い友達になれるかを考えます。また、勉強の大切さについても考え、自分の将来について真剣に向き合うようになります。
『君たちはどう生きるか』は、コペル君の成長を通じて、読者に「どう生きるか」という大きなテーマを問いかける作品です。コペル君の経験や叔父さんの教えを通じて、読者も自分自身の生き方について考えるきっかけを得ることができます。
この本は、いじめや友情、勉強など、中学生が直面するさまざまな問題をリアルに描いているので、共感しやすい内容になっています。また、コペル君の成長を見守ることで、読者も自分自身の成長について考えることができるでしょう。
5.『モモ』 – ミヒャエル・エンデ
『モモ』は、不思議な力を持つ少女モモが主人公の物語です。モモは町はずれの古い円形劇場に住んでいて、町の人たちは彼女に話を聞いてもらうと心が軽くなると感じています。モモはとても聞き上手で、どんな悩みも解決の糸口を見つけることができるのです。
ある日、町に「灰色の男たち」が現れます。彼らは「時間貯蓄銀行」というものを作り、人々に時間を預けるように勧めます。人々は時間を節約しようとしますが、実際には灰色の男たちに時間を奪われてしまいます。その結果、町の人々は忙しくなり、心の余裕を失ってしまいます。
モモはこの状況を見て、灰色の男たちの正体を暴こうと決意します。彼女の親友である道路掃除夫のベッポと観光ガイドのジジも協力します。モモは「時間の国」に住むマイスター・ホラという老人に出会い、彼から時間の秘密を教わります。マイスター・ホラは、時間を管理する存在であり、モモに時間を取り戻す方法を教えてくれます。
モモはマイスター・ホラの助けを借りて、灰色の男たちに立ち向かいます。彼女は「時間の花」という特別な花を使って、灰色の男たちの計画を阻止します。最終的に、モモは町の人々の時間を取り戻し、再び心の余裕を取り戻させることに成功します。
『モモ』は、時間の大切さや人間関係の重要性を教えてくれる感動的な物語です。モモの勇気と優しさが、多くの読者に感動を与えます。中学生にとっても、日常生活の中で大切なことを考えるきっかけになるでしょう。
6.『君の膵臓をたべたい』 – 住野よる
『君の膵臓をたべたい』は、内向的な高校生の「僕」と、明るくて元気なクラスメイトの山内桜良(やまうちさくら)の物語です。ある日、「僕」は病院で「共病文庫」という日記帳を見つけます。それは桜良が書いたもので、彼女が膵臓の病気で余命が短いことを知ります。
桜良は「僕」に、自分の病気のことを誰にも言わないように頼みます。そして、桜良は「僕」と一緒に過ごす時間を大切にしようと決め、二人は次第に仲良くなっていきます。桜良は「僕」をいろいろな場所に連れて行き、楽しい時間を過ごします。例えば、焼肉を食べに行ったり、スイーツバイキングに行ったり、旅行に行ったりします。
桜良は明るく振る舞いますが、時折見せる弱さや不安も「僕」に打ち明けます。「僕」はそんな桜良を支えようとしますが、自分の気持ちをうまく伝えられずに悩むこともあります。それでも、二人はお互いにとって大切な存在になっていきます。
しかし、桜良の病状は次第に悪化していきます。ある日、桜良は突然入院することになり、「僕」は彼女の見舞いに行きます。桜良は「僕」にもっと他の人とも関わるようにと言いますが、「僕」は桜良のことが気になって仕方ありません。
桜良が退院した後、二人は再び会う約束をしますが、その約束は果たされることはありませんでした。桜良は通り魔事件に巻き込まれて亡くなってしまいます。「僕」は桜良の死を受け入れられず、彼女との思い出を振り返りながら涙を流します。
最終的に、「僕」は桜良の親友である恭子(きょうこ)と友達になり、桜良の墓参りに一緒に行くことを決めます。『君の膵臓をたべたい』は、命の大切さや友情の深さを教えてくれる感動的な物語です。
7.『世界の中心で、愛をさけぶ』 – 片山恭一
『世界の中心で、愛をさけぶ』は、朔太郎(さくたろう)という高校生の男の子が主人公の物語です。朔太郎は、同級生のアキという女の子と恋に落ちます。二人はとても仲が良く、楽しい時間をたくさん過ごしますが、アキが白血病という病気にかかってしまいます。
アキの病気が進行する中、朔太郎は彼女を支え続けます。二人は一緒にオーストラリアに行くことを夢見ますが、アキの病状が悪化し、実現できません。それでも、朔太郎はアキのためにできることを全力で行います。
物語のクライマックスでは、朔太郎がアキを病院から連れ出し、空港に向かうシーンがあります。彼はアキをオーストラリアに連れて行こうとしますが、アキは空港で倒れてしまいます。朔太郎の必死の叫びが空港中に響き渡り、アキは救急車で病院に戻されます。
最終的に、アキは病気に勝てずに亡くなってしまいます。朔太郎は深い悲しみに包まれますが、アキとの思い出を胸に抱きながら前に進む決意をします。彼はアキの遺骨を持ち続け、彼女との思い出を大切にします。
『世界の中心で、愛をさけぶ』は、愛する人を失う悲しみと、それを乗り越えて生きる力を描いた感動的な物語です。朔太郎とアキの純粋な愛が、多くの読者の心を打ちます。
8.『バッテリー』 – あさのあつこ
『バッテリー』は、野球が大好きな中学生、原田巧(たくみ)と永倉豪(ごう)の物語です。巧はピッチャーとしての才能に自信を持っていて、父の転勤で岡山県の山間の町に引っ越してきます。そこで、同級生の豪と出会い、二人はバッテリーを組むことになります。
巧は自分の実力を信じて疑わないタイプで、周りの人たちが自分のすごさを理解していないことに苛立ちを感じています。一方、豪はキャッチャーとして巧を支える存在で、冷静で周囲に気を配ることができる性格です。
物語は、巧と豪が野球を通じて成長していく姿を描いています。巧は弟の青波(せいは)や家族との関係に悩みながらも、豪との友情を深めていきます。特に、巧が自分の弱点を認め、仲間と協力して乗り越えていく姿が感動的です。
また、巧の祖父である井岡洋三(いおかようぞう)は、かつて甲子園に出場した名監督であり、巧にとって大きな影響を与える存在です。祖父の教えを通じて、巧は野球の本当の楽しさや仲間の大切さを学んでいきます。
『バッテリー』は、野球を通じて友情や家族の絆、成長を描いた感動的な物語です。巧と豪のバッテリーがどのように成長していくのか、彼らの挑戦と絆が読者の心を打ちます。
9.『ビブリア古書堂の事件手帖』 – 三上延
『ビブリア古書堂の事件手帖』は、鎌倉の古本屋「ビブリア古書堂」を舞台にしたミステリーです。主人公は、古本屋の店主である篠川栞子(しのかわしおりこ)さん。彼女はとても美しいけれど、人見知りで初対面の人とはうまく話せません。でも、本に関する知識は誰にも負けません。
ある日、五浦大輔(ごうらだいすけ)という青年が、亡くなった祖母の遺品である『漱石全集』を持ってビブリア古書堂を訪れます。大輔は本を読むと体調が悪くなる「活字恐怖症」ですが、本に対する憧れも持っています。栞子さんは、この本にまつわる謎を解き明かし、大輔はその才能に感動します。
その後、大輔はビブリア古書堂でアルバイトを始め、栞子さんと一緒に古書にまつわる様々な謎を解決していきます。例えば、夏目漱石のサインが本物かどうかを調べたり、盗まれた本を探し出したりします。栞子さんの知識と推理力で、次々と謎が解かれていく様子がとても面白いです。
また、栞子さんの妹である文香(あやか)や、常連客の志田(しだ)さんなど、個性的なキャラクターも登場します。彼らとの交流を通じて、大輔は少しずつ成長していきます。
『ビブリア古書堂の事件手帖』は、古書にまつわる謎解きと、登場人物たちの成長を描いた心温まる物語です。中学生にも読みやすく、古書の世界に興味を持つきっかけになるでしょう。
10.『図書館戦争』 – 有川浩
『図書館戦争』は、近未来の日本を舞台にした物語です。この世界では、「メディア良化法」という法律が施行されており、政府が有害と判断した本やメディアを検閲しています。しかし、それに対抗するために「図書隊」という組織が存在し、自由な情報の流通を守るために戦っています。
主人公の笠原郁(かさはら いく)は、図書隊に憧れて入隊した新米隊員です。彼女は高校生の時に図書館で助けてもらった経験があり、その時の「王子様」に憧れて図書隊に入ることを決意しました。図書隊では、厳しい訓練や実戦を通じて成長していきます。
郁の上官である堂上篤(どうじょう あつし)は、厳しくも優しい指導者であり、郁にとって頼れる存在です。二人の関係は次第に深まり、物語の中で様々な困難を乗り越えていく中で、互いの信頼と絆が強まっていきます。
物語は、図書隊とメディア良化委員会との対立を軸に進んでいきます。郁たちは、検閲から本を守るために奮闘し、時には命をかけて戦います。彼らの勇気と情熱は、読者に感動を与えます。
『図書館戦争』は、自由と検閲という重いテーマを扱いながらも、キャラクターたちの成長や友情、恋愛が描かれており、中学生にも親しみやすい作品です。読んでいると、図書館や本の大切さを改めて感じることができるでしょう。
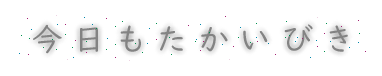



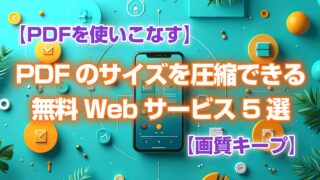






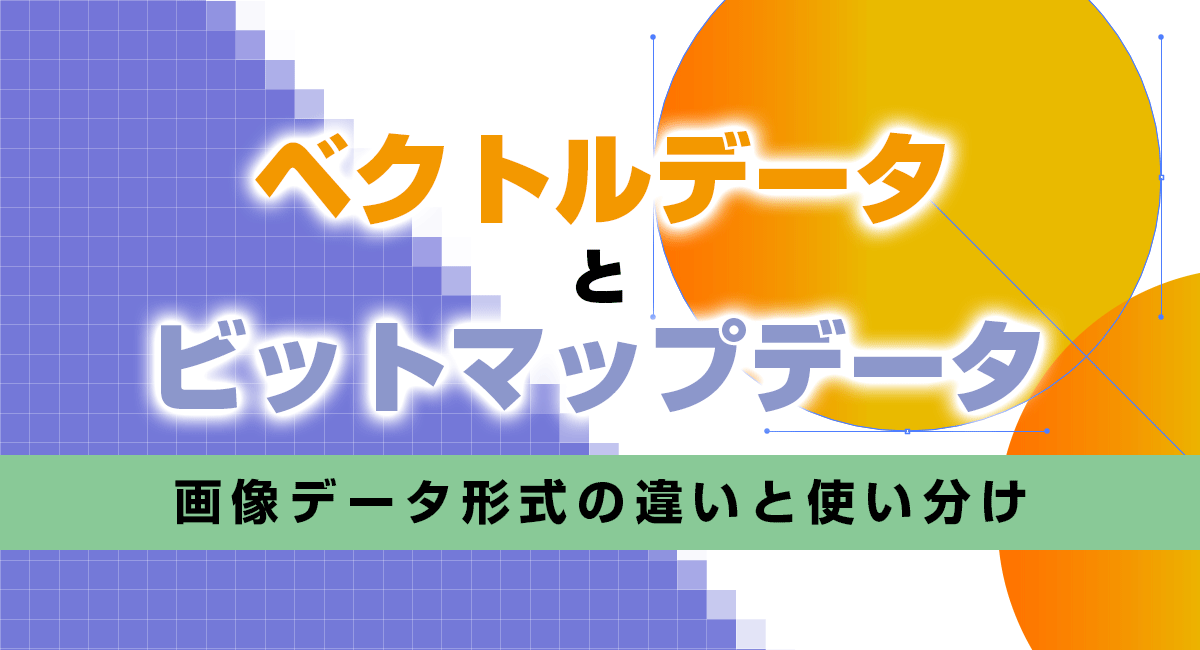

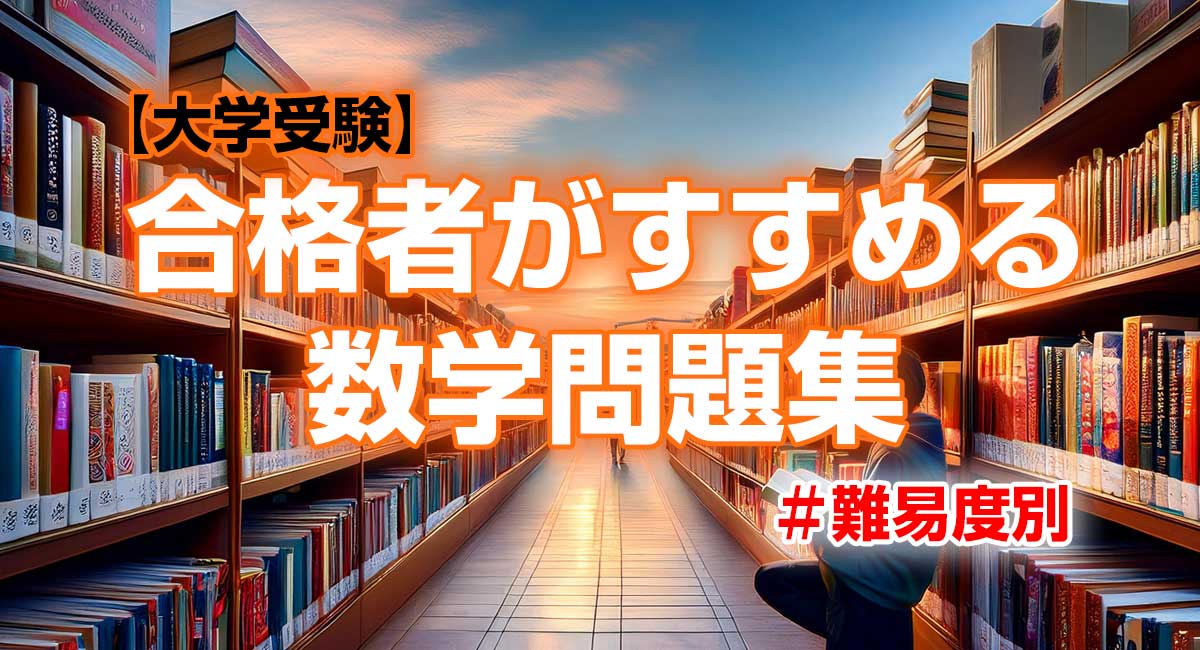



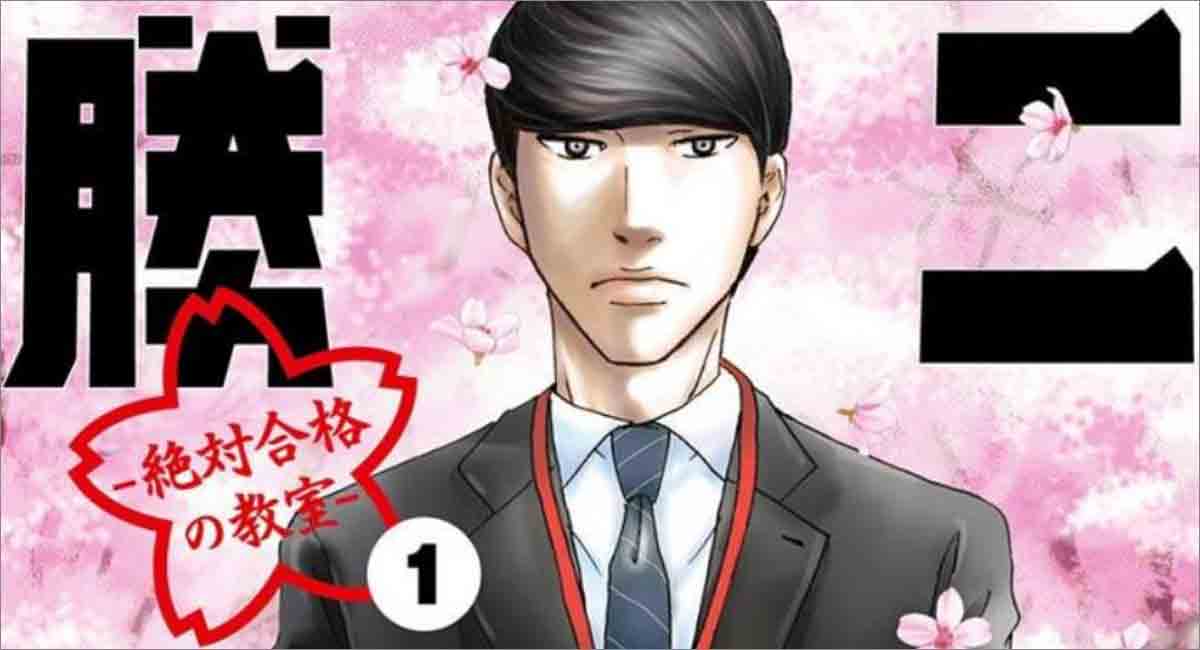



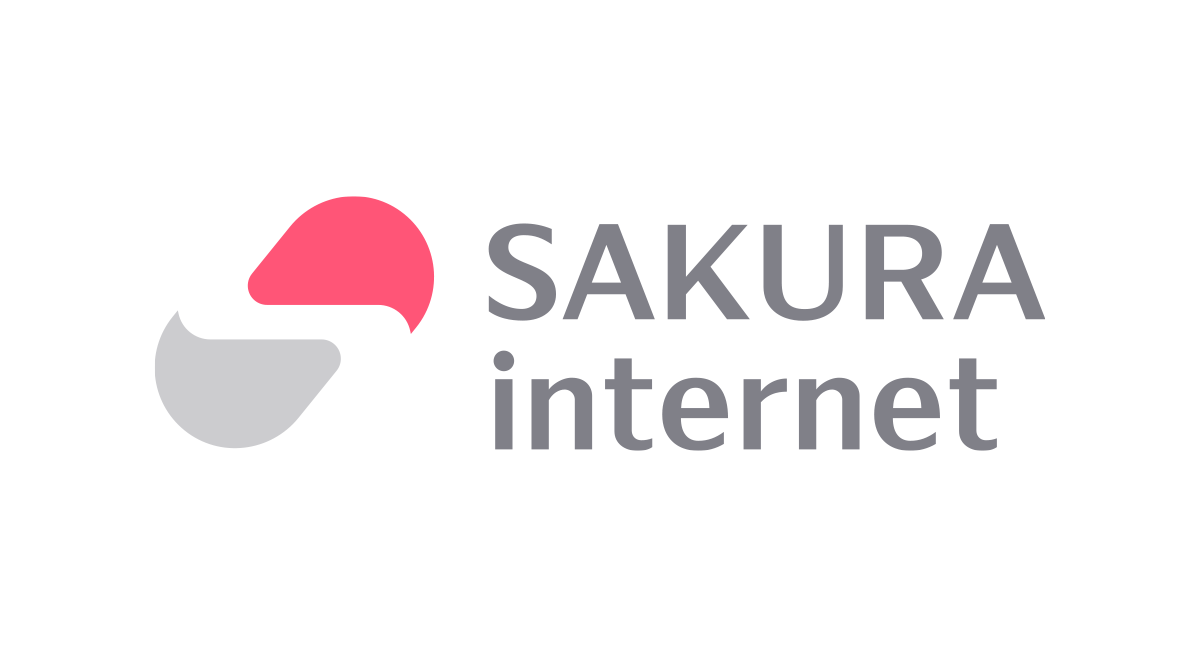


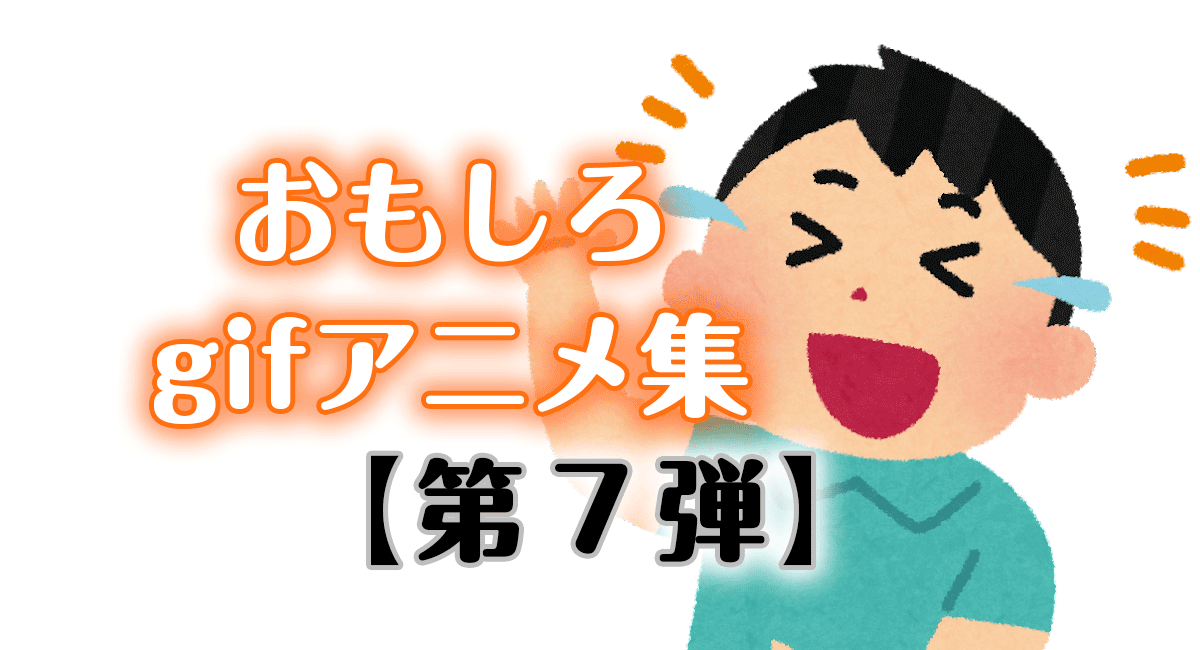
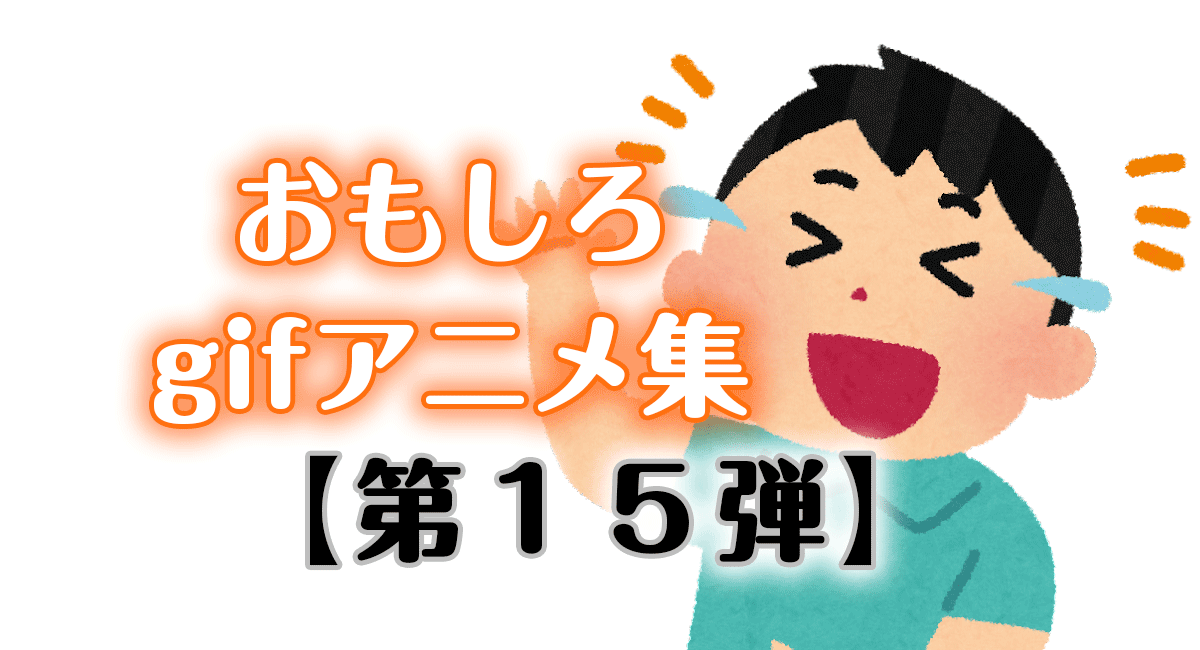



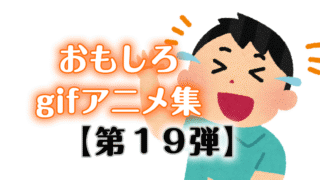



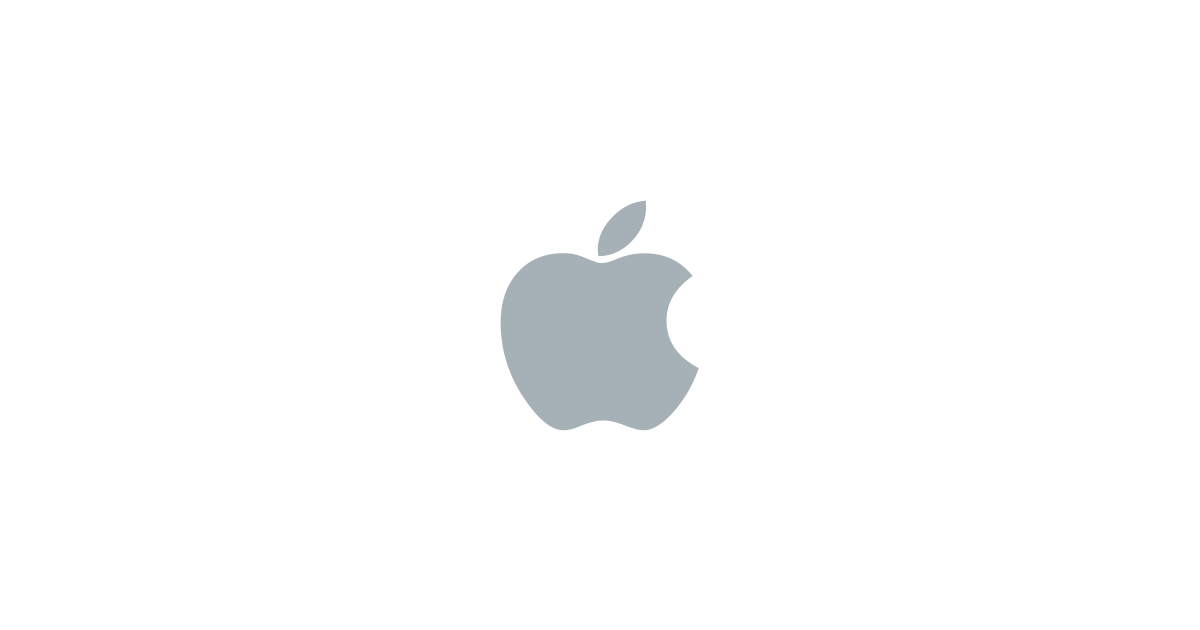




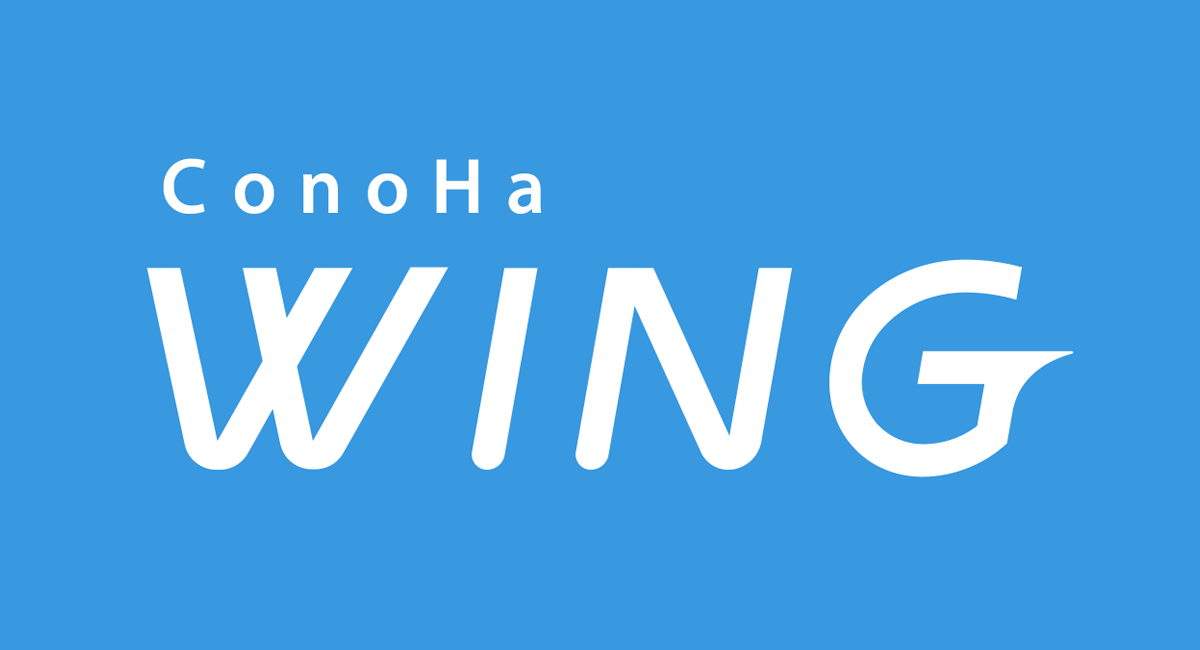

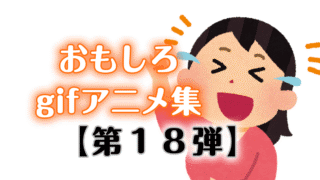
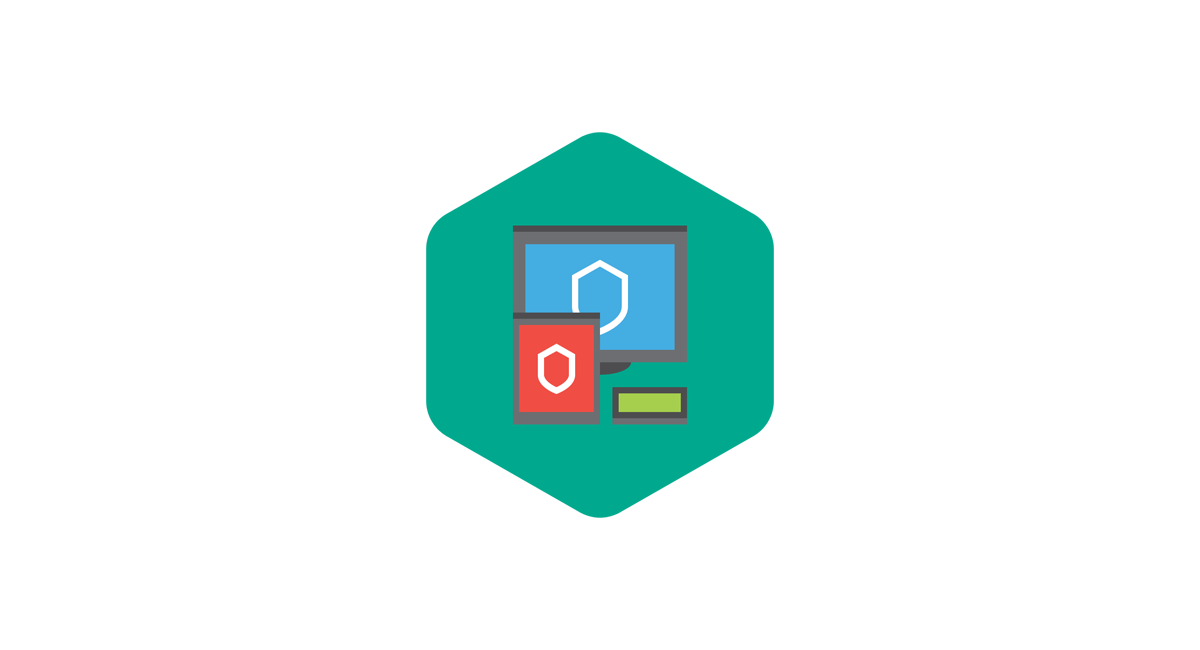



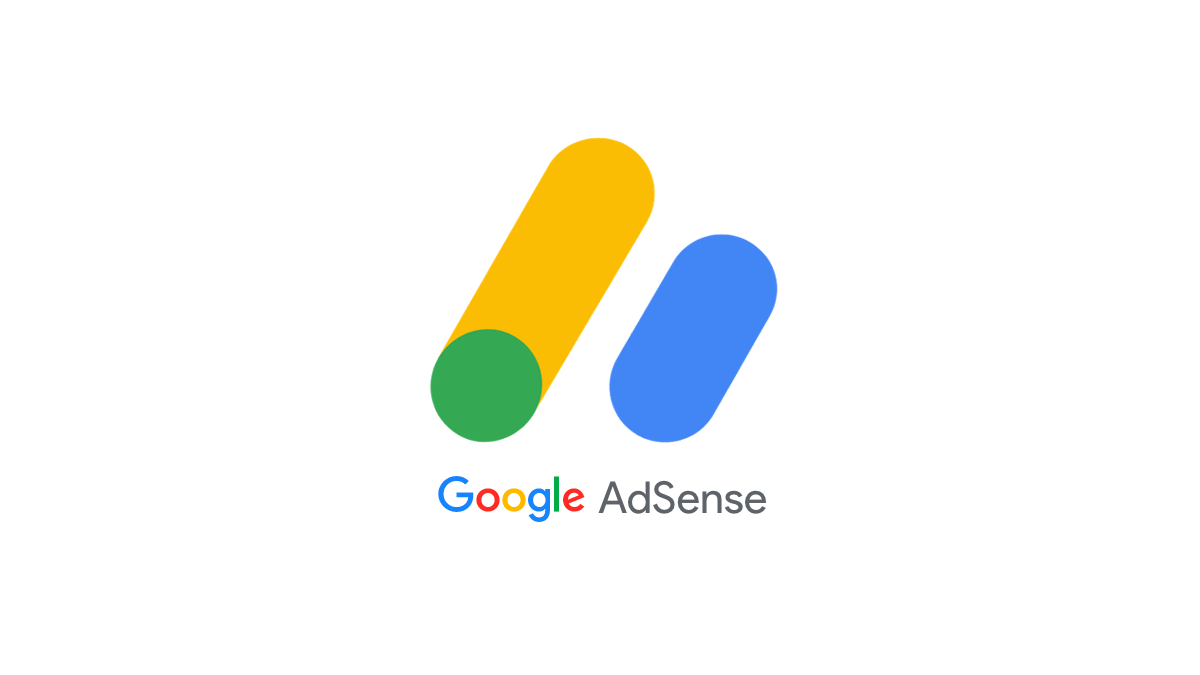


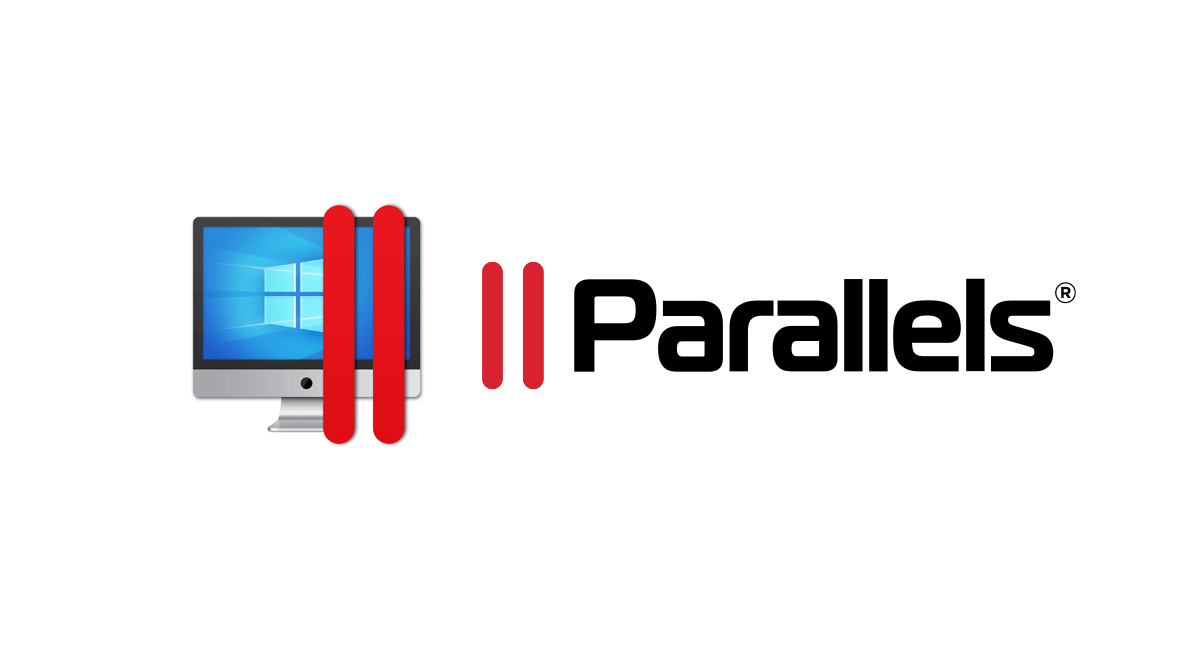


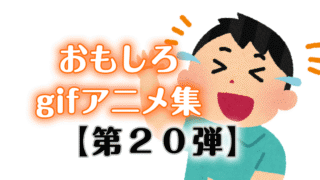
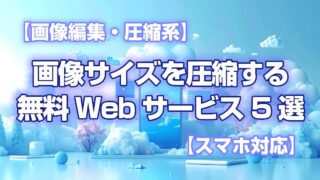
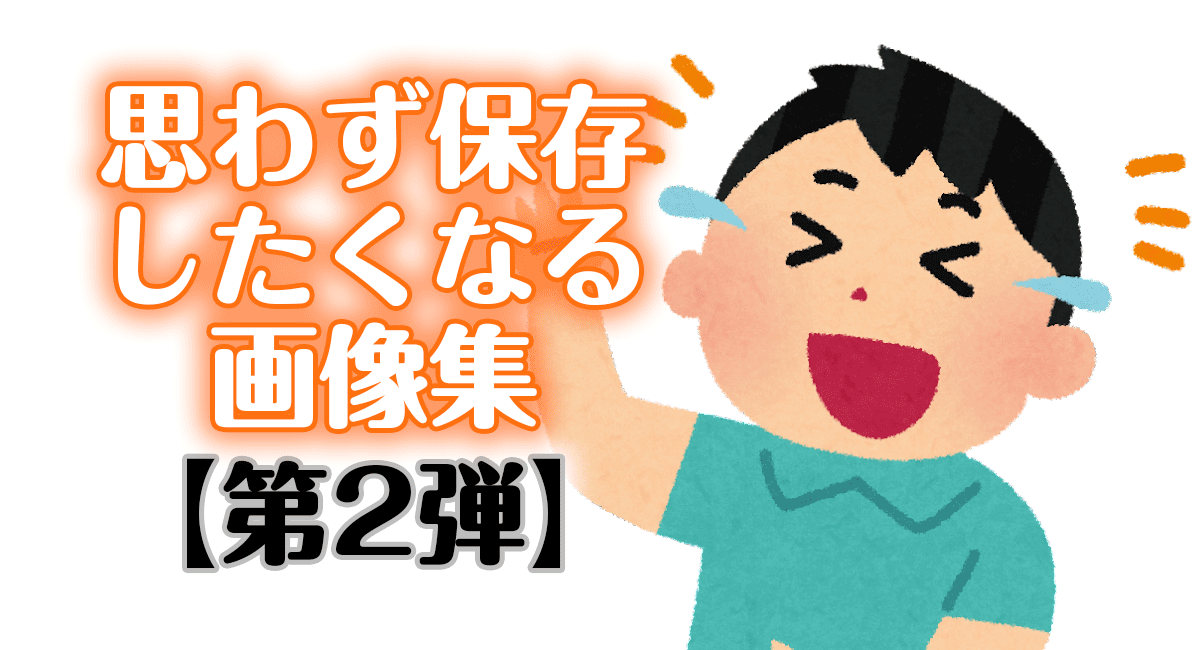

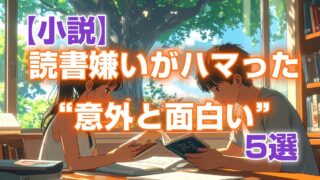


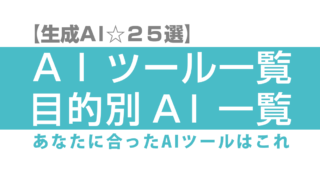
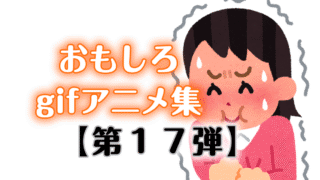
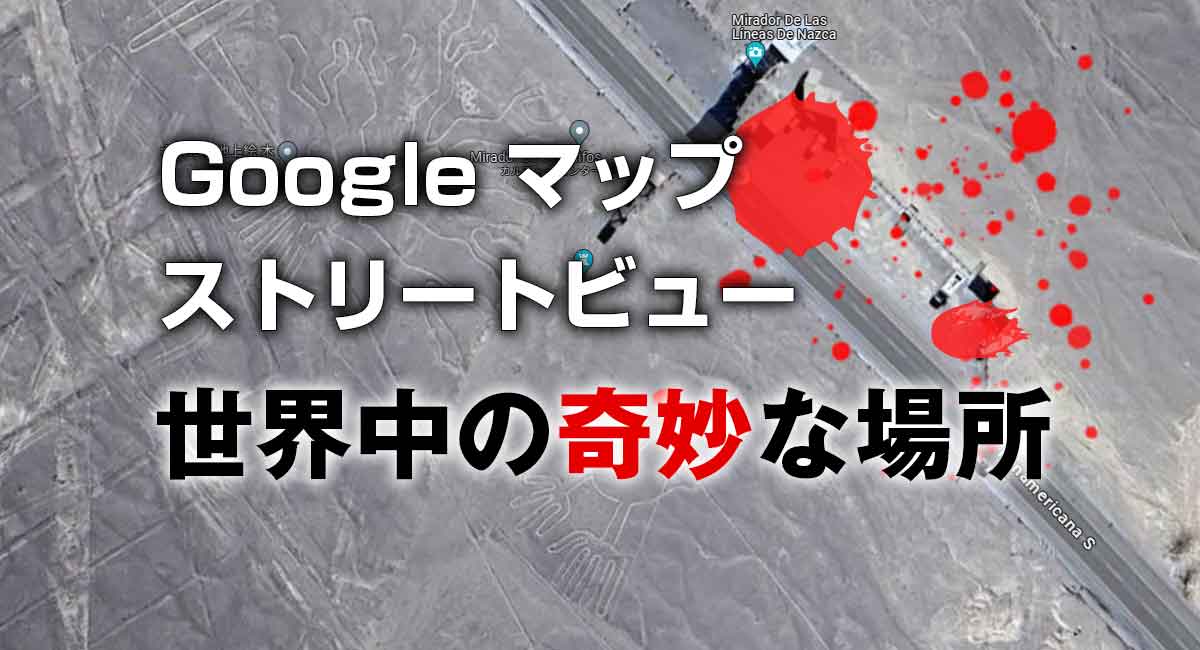
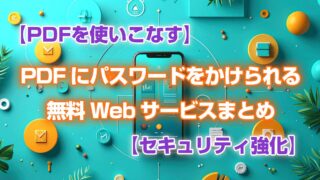



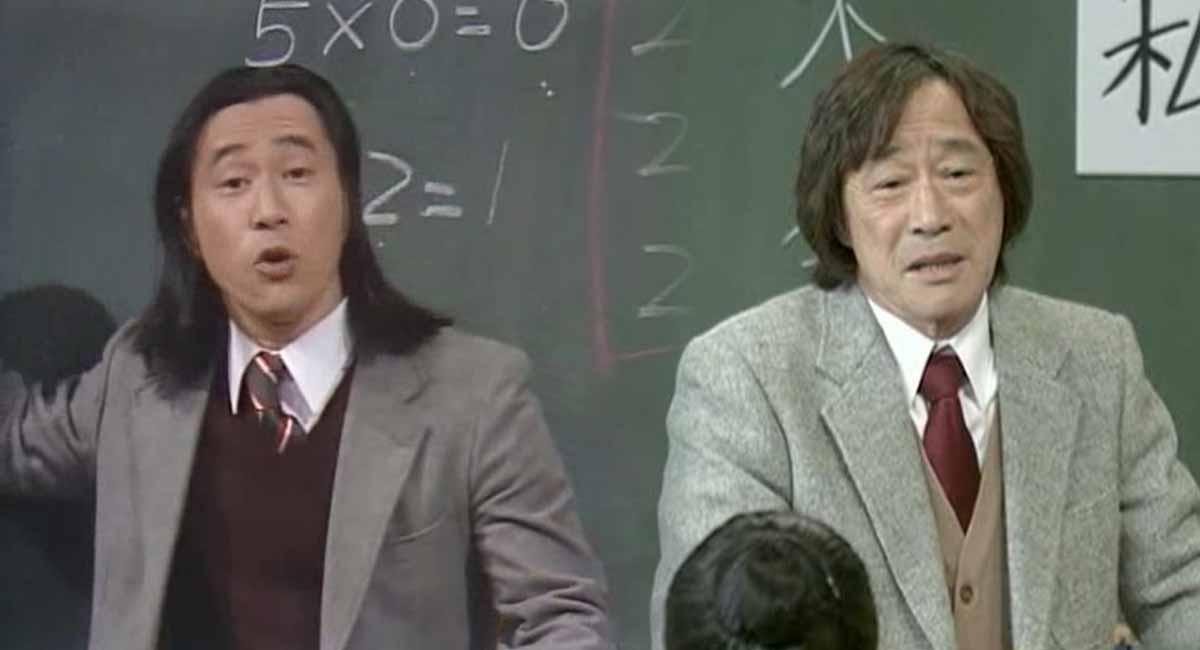
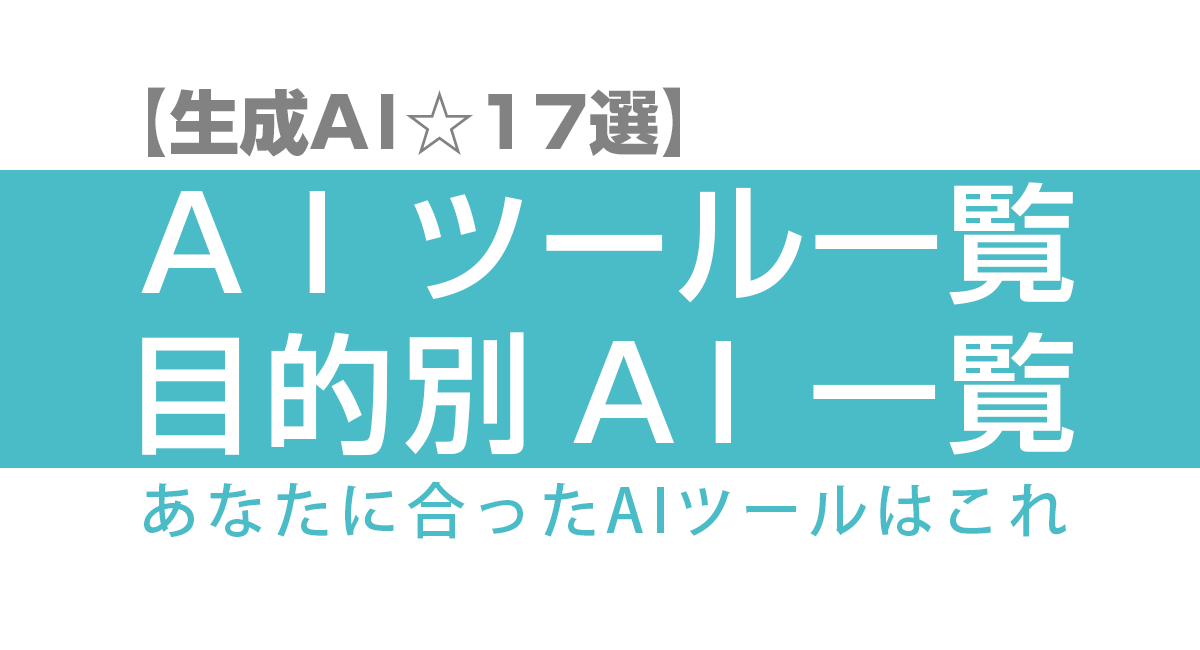
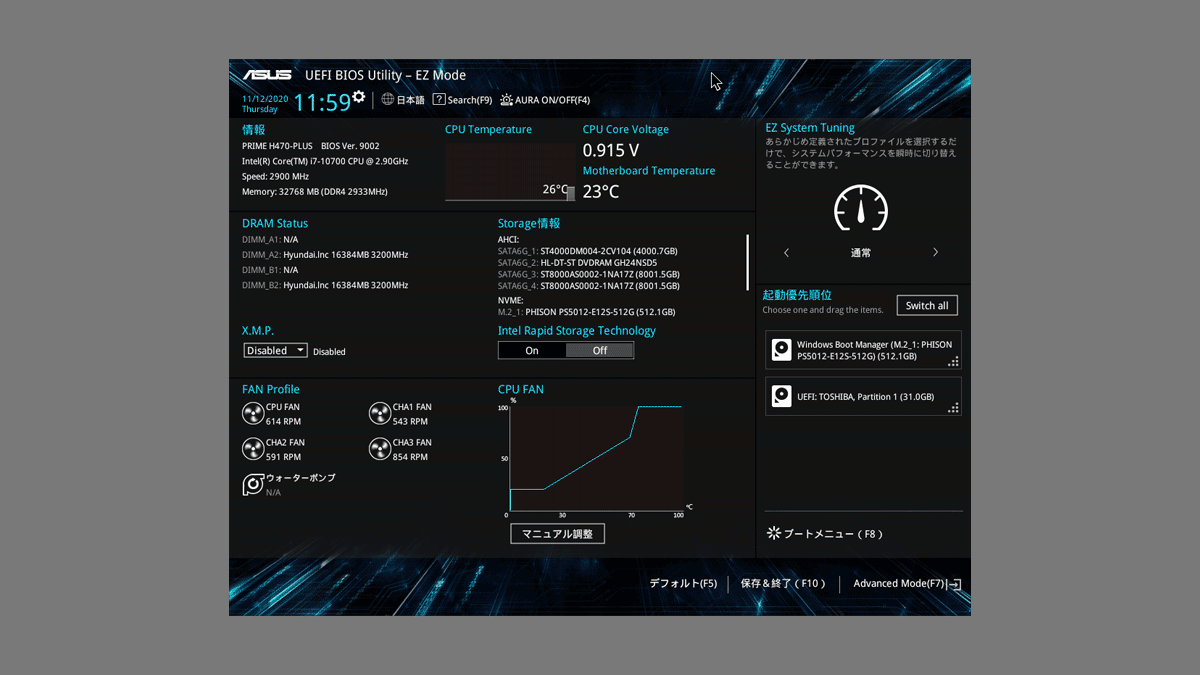






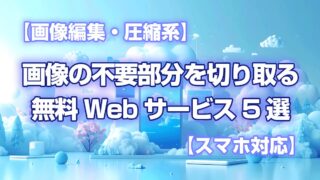


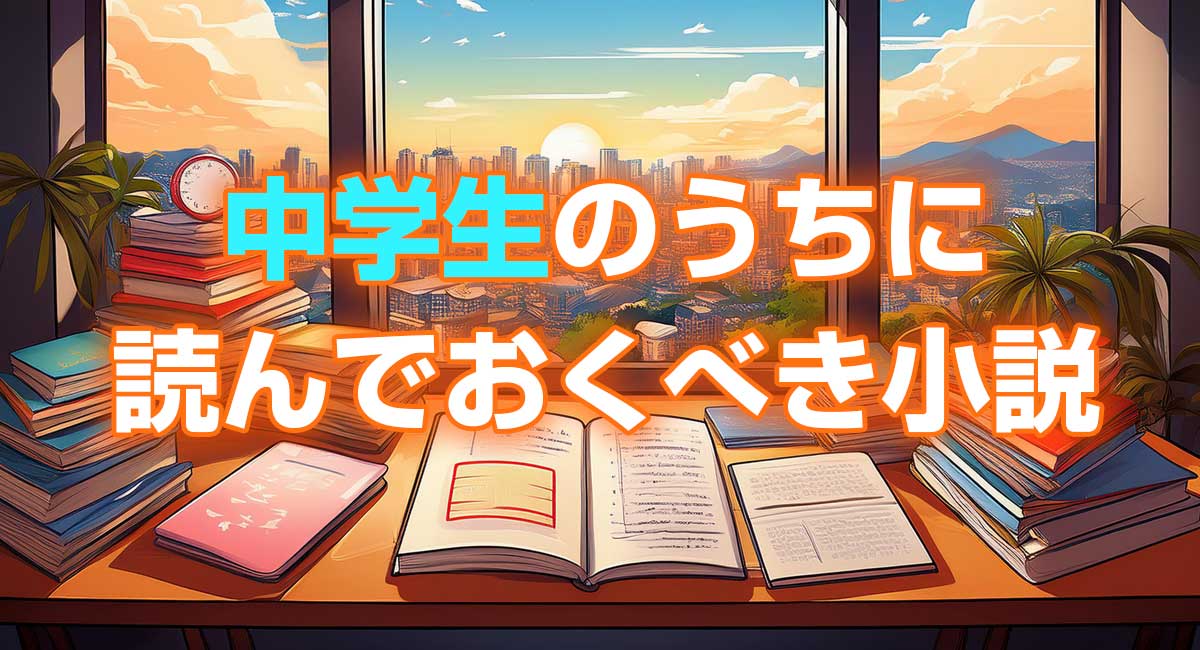



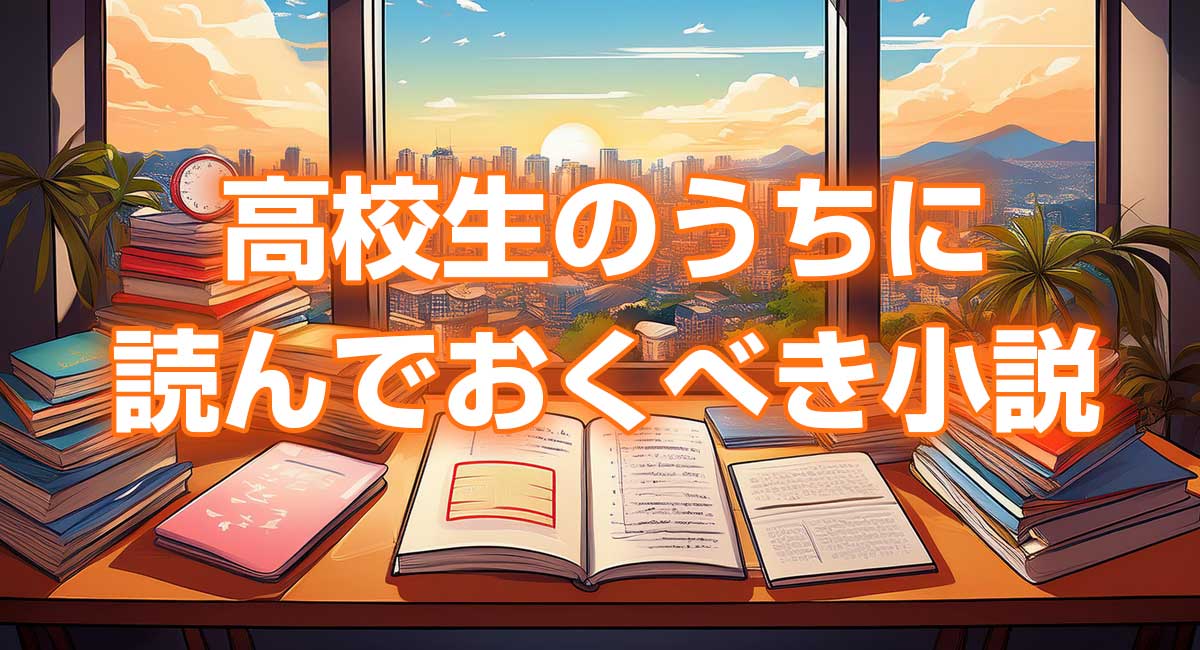
コメント